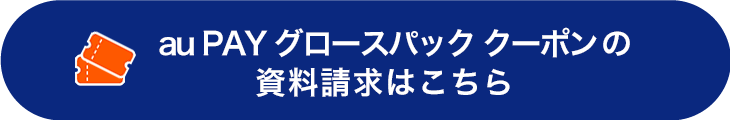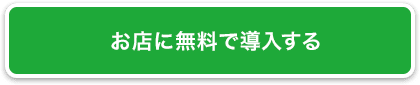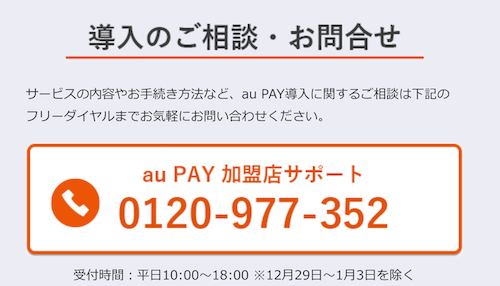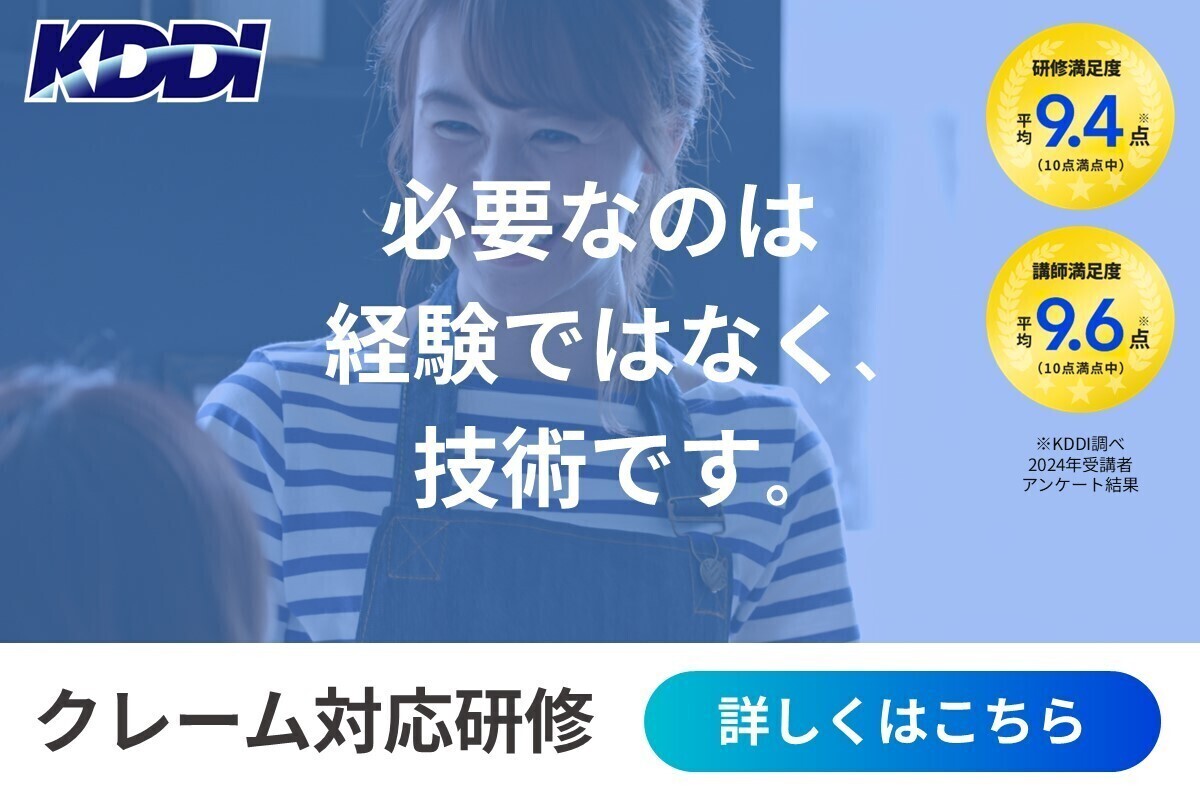国内のキャッシュレス決済の現状

QRコード決済をはじめ、近頃はあらゆるところでキャッシュレス決済が利用できるようになりました。キャッシュレス推進協議会の調査によると、2008年にはわずか11.9%だったキャッシュレス決済比率が、2019年には26.8%まで上昇しました。ただそれでも、キャッシュレス先進国といわれる韓国や中国のキャッシュレス決済比率は7割を優に超え、カナダ、オーストラリア、イギリスなどでも5割を上回ります。徐々に増えているとはいえど、日本国内のキャッシュレス決済比率は依然として国際的に低い水準にあることがわかります。
ただし、伸びしろがある日本では、キャッシュレス決済比率は今後も上昇していくでしょう。日本では少子高齢化が現在進行形で進んでいます。それによる人手不足がすでに問題視されており、社会全体で労働生産性の改善が求められています。さらに、2020年にはコロナウイルス感染拡大の影響により、非接触で支払いができるキャッシュレス決済の需要も高まっています。
政府もキャッシュレス決済の普及には前向きです。2025年までにキャッシュレス決済比率を4割程度まで上げ、2030年には世界最高水準のキャッシュレス社会を目指すという目標を打ち出しています。実際に、2019年には「キャッシュレス・ポイント還元事業」、2020年には「マイナポイント事業」が実施されました。特にキャッシュレス・ポイント還元事業は、キャッシュレス決済の使えるお店を大幅に増やすきっかけとなり、事業開始当初50万店ほどだった導入店舗数が、最終的には115万店にまで増えました。
DXやIoT、SaaSなどに代表される「デジタル化の波」は、今後もとどまるところを知りません。キャッシュレス先進国がそうであるように、日本でもキャッシュレス決済は今後も普及の一途をたどると予想されています。
小売業が導入できるキャッシュレス決済
キャッシュレス決済と一口にいっても、その手段はさまざまです。これからキャッシュレス決済の導入を進めたいという事業者の方のなかには、「どれが小売業のお店に最適なのか」と迷ってしまうこともあるでしょう。そこでまずは、現在どのようなキャッシュレス決済手段が小売業で導入されているのか、さらにそれぞれにどのような特徴があるのかを解説します。

■クレジットカード
電子マネーやQRコード決済が登場する前は、キャッシュレス決済といえばクレジットカードが主流でした。そのため日本でもすでに多くのお店で導入されており、大手のコンビニエンスストアやスーパー、百貨店などいろいろな場所で使えるようになっています。
経済産業省が行ったキャッシュレス決済実態調査アンケート集計結果(調査対象は全業種、回答数は1,189社。以降、実態調査)によると、クレジットカードを導入しているのは全体の55%。さらに業種別に見ると「食品小売」は45%、「その他の小売」は73.8%という結果になっています。また、売上規模別では、「1000万円未満」のみ導入率が平均を下回る40.8%となっており、1,000万円以上の店舗ではのきなみ半数を超えています。
クレジットカードの導入には専用の端末が必要なため、導入費用がかかります。また売上規模が低くなるごとに、決済手数料率が上がる傾向にあります。そのような理由から、中小規模の店舗ではクレジットカードの導入があまり進んでいないという現状が読み取れます。
■電子マネー
電子マネーは、現金を電子化してデジタルでお金のやりとりを行うキャッシュレス決済のことです。「Suica」を始めとする交通系ICが代表的な例。定期券に電子マネー機能が付いたものも一般的で、クレジットカード同様、自動販売機やコンビニエンスストアなどで利用できます。チャージをした金額以内のみでお買い物ができるため、その場合は使いすぎの心配が少ないのが特徴です。
また、近年ではイオンの「WAON」、セブン&アイ・ホールディングスの「nanaco」、CGCグループの「CoGCa」など、小売業自身が発行する電子マネーも広がっています。ただそれでも、小売業での電子マネー導入率は、クレジットカードよりも低く、3割程度にとどまっています。
■QRコード決済
QRコード決済は、スマートフォンやタブレット端末でQRコードを読み取ることで支払いができる決済方法です。読み取り方法は2方式あり、店舗側がユーザーのスマートフォンに表示されているバーコードを読み取る「CPM(顧客提示型)」と、ユーザーが店頭に表示されたQRコードを読み取る「MPM(店舗提示型)」があります。スマホひとつでお買い物ができるという手軽さから、日々の小さなお買い物でよく使われる傾向にあります。
2010代後半になって日本でも普及するようになり、比較的新しいキャッシュレス手段といえるでしょう。ただそんな歴史の浅いQRコード決済は、クレジットカードに迫る勢いで普及が進んでいます。実態調査では、QRコード決済の導入率は「食品小売」で62.5%、「その他の小売」で71%となっています。売上規模別に見ても、1,000万円から10億円規模の店舗まで総じて5割前後となっており、お店の大小を問わず導入されています。
その背景には「QRコード決済の導入のしやすさ」があると考えられます。QRコード決済の導入に際しては、専用端末など初期投資が不要です。お客さんが提示したQRコードを読み取る場合も、一般的なスマホ・タブレットで代用可能です。ほかのキャッシュレス手段と比較して、費用面に優位性があるため、ここまで広く導入が進んでいるのです。
小売業者がキャッシュレス決済を導入すべき理由
ここまでは小売業のお店で導入されている主要なキャッシュレス決済手段を紹介しました。続いてはより具体的に、小売業者がキャッシュレス決済を導入するメリットを考えてみましょう。

■会計時間の短縮
キャッシュレス決済は、会計の作業時間を短縮できます。例えば現金決済の場合、会計時にはレジの店員がお客さんから現金を受け取り、レジに情報を入力し、お釣りを渡す必要があります。細かい小銭で支払われたら、間違いのないように丁寧に金額を計算する必要もあるでしょう。
一方、キャッシュレス決済の場合はそのようなことがなく、カードを読み取ったり、QRコードをスキャンしたりするだけで決済が完了します。忙しい時間帯にできるレジの行列も、キャッシュレス決済比率が上がればおのずと短くなるはずです。
■現金管理の手間軽減
キャッシュレス決済で支払いをするお客さんが増えると、現金の取り扱い総量が減っていきます。そうなれば、毎日のレジ締めで数える現金が減り、業務効率化につながります。
野村総合研究所の資料によると、レジ1台あたりの「レジ現金残高の確認作業」平均時間は25分。これに売上集計や両替、釣り銭の用意などの作業をくわえると、日々そうとうな時間を現金にまつわる業務に割いていることがわかります。この業務の原価はほとんどが人件費といっても差し支えないでしょう。
キャッシュレス決済を導入することで、業務効率化を図ることができ、コスト削減も期待できます。さらに現金の総額も減るため、盗難や強盗などのリスク軽減にもつながります。
■新たな客層の集客
キャッシュレス決済サービス各社は、独自のポイント還元キャンペーンを行っています。少しでもおトクにお買い物や食事をするために、現金ではなく特典のあるキャッシュレス決済を積極的に使う消費者も少なくありません。
お店にキャッシュレス決済を導入しておくことで、消費者に選んでもらえるようになるのです。
小売業者がキャッシュレス決済を導入する際の注意点
キャッシュレス決済を導入するメリットは上記で紹介した以外にも、衛生的であること、決済データを売上分析や顧客分析に利用できることなどが挙げられます。一方で、小売業でキャッシュレス決済を導入する際に、知っておいていただきたい注意点もあります。ここでは小売業のキャッシュレス化を阻む「決済手数料」・「初期費用」・「入金サイクル」の3つの壁について解説していきます。

■決済手数料
クレジットカードを始めとするキャッシュレス決済では原則、決済手数料がかかります。決済手数料の相場は業種やお店の規模によって異なり、クレジットカードの場合、平均約3~4%といわれています。小売り企業の売上高営業利益率が2%前後といわれるなかで、この料率は決して小さくはありません。実際に、キャッシュレス決済を導入していないお店でその理由を聞いてみると、「手数料が高い」という声をよく耳にします。
ただし、逆に会計時間の短縮などにメリットを感じる小売業者も多く、実態調査ではすでにキャッシュレス決済を導入している店舗の半数以上がキャッシュレス決済の利用を増加させたい、または維持したいと答えています。
■初期費用
決済手数料のほかに、キャッシュレス決済導入には初期費用もかかります。初期費用がかかるのは、主に専用の端末が必要となるクレジットカードと電子マネーです。初期費用にかかる額は導入するサービスによって異なりますが、数万円から十数万円の設備投資がかかることもあります。キャッシュレス決済の導入によって実際にどのくらいのメリットが得られるかわからない状況では、決して簡単な経営判断ではありません。特に経営資源が潤沢にない中小規模の小売業では、初期費用は大きなボトルネックとなっています。
■入金サイクル
小売業のお店がキャッシュレス決済を導入しづらい理由に、「入金サイクルが遅い」ことも挙げられます。キャッシュレス決済が成立したその場ではお店側は売上金を受け取れず、一定期間まとめた売上金が後日振り込まれるのが一般的です。「月末締め翌月入金」「月2回の入金」など、サービス各社対応は異なりますが、入金サイクルのスパンが長ければ長いほど、手元にお金が入るのが遅くなります。
キャッシュレス化を一気に進めて、お店のキャッシュフローを圧迫する事態となっては元も子もありません。導入するキャッシュレス決済手段を選ぶ際には、「入金サイクルがどうなっているのか」、「入金手数料がかからないどうか」という点もしっかりと確認するようにしましょう。
au PAY、今なら初期費用・決済手数料が無料!
小売業者がキャッシュレス決済を導入する際に注意したい3つの壁は、「決済手数料・初期費用・入金サイクル」でした。そして「au PAY」なら、この3つの壁をすべてクリアできます。
au PAYは2022年9月30日まで決済手数料無料キャンペーンを行っています。もともとこのキャンペーンは2021年中に終了予定でしたが、新型コロナウイルスが蔓延している社会情勢を鑑みて、延長することを決定しました。なお、キャンペーン終了後の手数料率は現時点で2.6%としており、こちらもキャッシュレス決済の業界水準を下回るものとなっています。
また、au PAYはQRコードを通じて決済を行うので、専用端末も不要です。プリントしたQRコードをお店に掲示するだけではじめることができ、お客さんのQRコードを読み取る場合もスマホやタブレットなどで問題ありません。
入金サイクルについては月1回、月2回、早期振り込みサービスの3つの選択肢を用意しています。本来であれば早期振り込みサービスを利用すると入金ごとに210円の事務手数料が発生しますが、こちらも新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮して、当面の間無料となっています。
まとめ
国内のキャッシュレス普及率は年々増加しています。すでに説明したように業務効率化や顧客獲得など、小売業にとってもキャッシュレス決済を導入することのメリットは大きいといえます。ただし、導入に際しては費用面や資金繰りについてしっかりと検討する必要があります。お店の状況に合わせて、適切なキャッシュレス決済手段を選ぶようにしましょう。
なお、これからお店のキャッシュレス化を進めるのであればQRコード決済の「au PAY」からはじめてみてはいかがでしょうか。2022年9月末まで決済手数料が無料で、初期費用も不要です。加盟店向けの24時間サポートも用意しており、大規模店舗はもちろんのこと中小規模店舗の事業者様にも安心して導入していただけます。ぜひこれを機に、au PAYの導入を検討してみましょう。