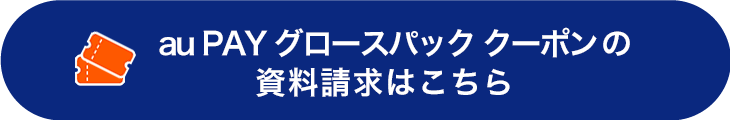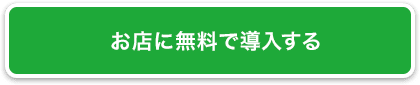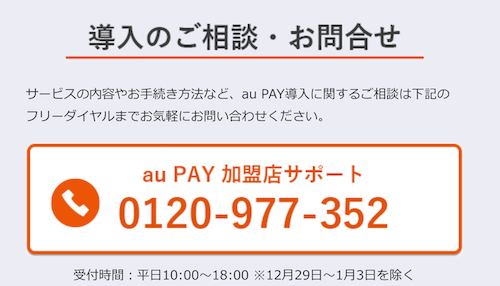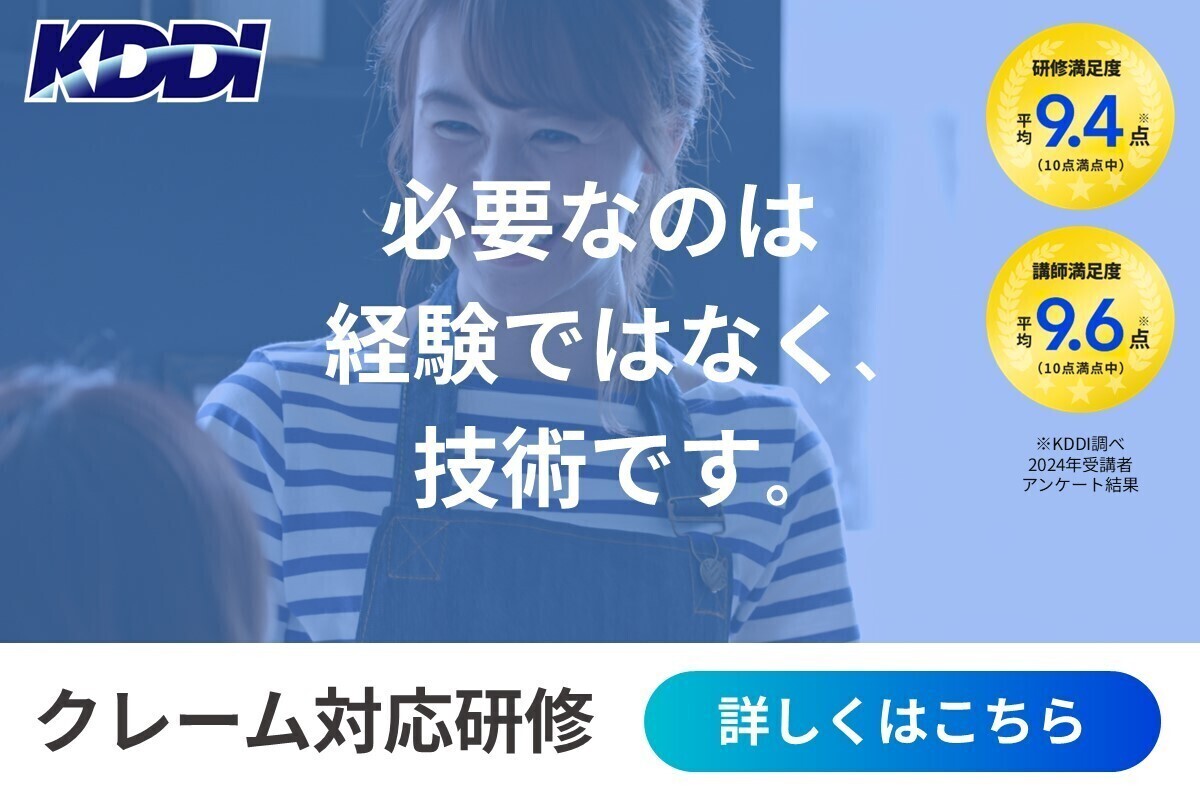日本のキャッシュレス決済比率は20%強で、政府は2025年に40%を目標に

ここでは日本のキャッシュレス決済がどのくらい普及しているのか、そして今後どの程度まで広がりを見せるのかを見てみましょう。
■日本の現在のキャッシュレス決済比率
ここ10年で毎年1~2%ほど増えており、2019年にQRコード決済サービスが数多く登場したこと、さらには新型コロナウイルス蔓延による衛生意識の高まりによって現在のキャッシュレス決済比率はもう少し高いと予想されます。
なお、「キャッシュレス支払手段による年間支払い金額÷国の民間最終消費支出」で算出されるキャッシュレス決済比率ですが、その内訳のほとんどはクレジットカードが占めています。
■政府の目標は2025年までに倍増の40%、将来的には80%を目指す
実は日本のキャッシュレス決済比率は決して高くありません。世界の先進国のキャッシュレス決済比率はおおむね40~60%台となっていて、たとえばお隣の韓国は2015年時点で89%に達しています。そのため、日本政府は2025年までに比率を40%まで引き上げ、さらには将来的に80%という世界最高水準を目指すとしています。
■QRコードを規格統一する「JPQR」という取り組みも
QRコード決済サービスで使われるQRコードは、各社それぞれの独自仕様となっています。そこでそれらを統一するために進められているのが「JPQR普及事業」です。
そもそもQRコードはバーコードが進化したものです。バーコードは縦方向の縞模様をスキャンして、その線の太さ・間隔により固有情報を読み取っていました。加えて、QRコードでは縦横両方に模様を表現することで、より多くの情報を盛り込めるようになりました。
ただ、いろいろな情報をどうやってQRコードに収めるかは、決済事業者それぞれが独自の仕様で決定していました。規格がバラバラではお店側も利用者側も使い勝手が悪く、普及も進んでいきません。そこで規格を統一して使いやすくしようというのが「JPQR」です。2019年に発足したばかりの事業なので、まだまだ知名度・普及率ともに高くないものの、JPQRが普及すればより一層利便性が高くなると考えられます。
キャッシュレス決済が広がることによるメリットと普及に向けた課題

それではなぜ、国を挙げてキャッシュレス決済比率を高めようとしているのでしょうか。続いては、キャッシュレス決済が広がることによるメリットを「社会」「利用者」「事業者」の各視点から考えていきたいと思います。
■社会的なメリット
国主導でキャッシュレス決済を広めるには、それなりの理由というものがあります。それは大きく以下の3つが考えられます。
・人手不足/生産性向上
・現金取り扱いコスト
・インバウンドの拡大
まず一つ目は少子高齢化による人手不足です。全体の人口が減っていく中でGDPを維持するためには労働生産性を上げるしか方法がありません。キャッシュレス決済が普及することで、社会全体の効率化を図れます。
キャッシュレス決済にはレジにまつわる業務を短縮化する効果や、キャッシュレス決済比率向上に伴う取引のデータ化が新たな価値を生むとされています。そこから新産業が発展する可能性も考えられるため、キャッシュレス決済比率を高めることはイノベーションのきっかけにもなると期待されています。
2つ目は現金の取り扱いコストです。現金決済のインフラを維持するのにもお金がかかっていることをご存じでしょうか。たとえば、造幣局の貨幣製造コスト、銀行の店舗設備投資や現金輸送費、ATM機器費・設置費、さらには詐欺や強奪による現金被害など。現金決済のインフラ維持費は推計で年間1.6兆円にも上ります。1.6兆円といえば、ちょうどGo To キャンペーン事業の予算と同じぐらいの規模なので、決して少ない数字ではないことがわかります。
3つ目のインバウンド拡大については、特に中国からの訪日観光客を意識したものとなります。中国ではキャッシュレス決済比率が60%以上と高く、中国人観光客はあまり現金を持たない傾向にあります。
経産省の資料でも「クレジットカード等が利用できる場所が今より多かったら、もっとお金を使っていた」と回答した割合が4割近くにも上ります。感染症が流行っているなかでは海外からのインバウンド需要があまり期待できないものの、日本のキャッシュレス化が遅れているために機会損失が出ていたことがわかります。
このような理由によりキャッシュレス決済が増えることは社会的な意義を持つとされるのです。
■利用者側のメリット
利用者のメリットもいくつか考えられます。まず挙げられるのが現金不要であるために「利便性が向上」する点です。
たとえば、現金のみで支払いをおこなう人のケースを考えてみましょう。その場合、当然手持ちの現金がなければ買い物はできません。そして財布の中身がなくなるごとにATMに行き、お金を下ろさなくてはなりません。では、キャッシュレス決済ができればどうでしょうか。おそらくATMで現金を下ろす頻度が減り、仮に手持ちのお金がなくとも買い物ができることでしょう。このように複数の決済方法を持つことによる利便性の向上効果は決して少なくありません。
また、財布を紛失したり盗難されたりした場合でも、被害リスクを最小限に抑えられます。常にある程度の金額を持ち歩いている場合、財布を落とした時にもそれだけ被害が大きくなります。しかし、キャッシュレス決済を主としていれば、現金は必要最低限だけを持つようになります。
クレジットカードやQRコード決済では、不正利用は(条件次第で)保証される場合がほとんどです。利便性だけでなく、リスク回避にも役立ちます。
ほかにもいろいろなメリットがあります。たとえば、キャッシュレス決済であれば、支払い履歴がデータとして残ります。家計簿と連携するなど家計の管理や節約にも役立ちます。さらにキャッシュレス決済サービスの多くはポイント還元がされます。お買い物の金額に応じて、それぞれのポイントがたまるようになっており、現金よりもお得に買い物ができるのも大きなメリットの一つです。
■事業者側(お店側)のメリット
事業者にとってもキャッシュレス決済は良い面がたくさんあります。
たとえば、お店にとってのレジ締め作業というのは簡単な仕事ではありません。特にレジ金額残高の確認作業は多くの時間が割かれており、野村総合研究所の資料によれば1店舗1日当たり平均延べ153分がレジの現金残高の確認作業に充てられています。
キャッシュレス決済が増えれば、それだけ現金の取扱量が減り、業務効率化につながります。さらには売上金紛失や盗難などのトラブルも起きづらくなるでしょう。現金の搬入出回数が減れば強奪リスクも下がり、それにともなうコストも抑えられます。
また現金のやり取りが減ることは衛生的にも良い影響を与えます。紙幣や硬貨に雑菌が付着していることは、数々の研究で示されています。現金決済ではそういったお金を日常的にやり取りしなくてはいけないため、衛生面から考えると非接触型決済に劣ります。
さらに新型コロナウイルス感染症の蔓延により、人々の衛生意識はさらに高くなっています。現金決済を減らすことは、従業員やそのお店の利用者がウイルスを媒介する機会の削減につながります。各業界の新型コロナウイルス感染症のガイドラインでも、小売業や外食業、旅行業、劇場、音楽堂などの業種で「電子決済を増やすことで非接触型決済を推進する」旨の内容が盛り込まれています。
そのほかにも、売上や集客に関する効果も期待できます。キャッシュレス決済サービスの多くは、各サービス独自の還元ポイントを用意しています。たとえば、au PAYでお買い物をするとPontaポイントがたまるといった具合です。au PAYが使えるということは、au PAYユーザー約2,300万人への立派なアピールポイントになりえます。
「キャッシュレス・ポイント還元事業」でキャッシュレス決済を導入する事業者が増えた

政府の「キャッシュレス・ポイント還元事業」を覚えているでしょうか。「キャッシュレス・ポイント還元事業」とは2019年10月1日に8%から10%へと移行した消費増税にあわせて、キャッシュレス化を推進するための事業です。対象期間は2019年10月1日~2020年6月30日で、この間に還元対象のお店でキャッシュレス決済を行うと最大5%のポイント還元を受けられるという内容でした。
すでに終了した事業であるため、経産省がこの事業を総括する資料を公開しています。それを見ると、キャッシュレス決済がどれくらい人々に受け入れられているのか、キャッシュレス決済を導入したお店がそれをどう感じているのかがよくわかります。ここでは最後に、ポイント還元事業のレビューの中身を簡単にご紹介していきます。
■還元事業ではQRコード決済が急増
結論から言うとポイント還元事業によりキャッシュレスを利用する消費者もお店も増えたといえます。この事業をきっかけにキャッシュレス決済を初めて使った、あるいは増やしたと答えた割合は回答者全体の51.5%。キャッシュレス決済の種類ごとにも特徴がみられます。
2019年6月と2020年5月の各決済方法の利用頻度を比較すると、最も利用されているのがクレジットカードで、次が電子マネーです。さらに、この期間中もっとも伸び率が高かったのが「QRコード決済」です。利用者の割合は28.5%から46.3%にまで上昇しています。
年代別の利用率をざっくりと見てみると、クレジットカードは50代・60代の利用が比較的多く、デビットカードは20代、交通系電子マネーは10~20代、QRコード決済は20~40代に多い傾向です。それぞれにユーザーの特徴があり、お店側はこれを参考にして狙う客層に合わせてキャッシュレス決済方法の選択をするといいでしょう。
■導入店舗の9割がキャッシュレス決済の提供を続ける意向
さて、事業者側にはどのような変化が見られたのかを確認しておきましょう。還元事業参加店舗の69.7%が「はじめてキャッシュレスの支払い手段を導入した、あるいは増やした」と回答しています。さらには、約半数のお店がキャッシュレス導入により業務効率化効果が得られたと答えています。
また、還元事業終了後もキャッシュレス決済の対応を続けるとした参加店舗は9割に上ります。ここからもキャッシュレス決済の導入への満足度の高さがうかがえます。
ただし一方で、課題も残ります。先の質問に「キャッシュレス決済への対応を継続しない」理由として多かったのが次のような内容です。
・当初想定よりも決済手数料などの費用が割高だったから
・キャッシュレスの支払い手段を利用する顧客が少ないから
・入金されるまでに一定日数以上かかるため、資金繰りに困ることがあったから
これが上位3つの理由です。とはいってもそれぞれ全体の2~5%ほどなので、ほとんどの事業者はキャッシュレス決済への対応に効果を感じていると言えそうです。
まとめ
国際的に見てキャッシュレス比率が高いとは言えない日本。政府は将来的に40%、さらには80%まで引き上げることを見据えています。そのため今後も、官民連携したキャッシュレス化への動きは引き続き活発になっていくでしょう。
現金決済のコストや日本の少子高齢化の状況を鑑みれば、キャッシュレス決済の普及は不可欠ともいえるかもしれません。キャッシュレス決済サービスがより多様化していけば、それだけ選択肢が増え、利便性が高まります。社会、ユーザー、事業者、それぞれにとってメリットがあるため、キャッシュレス決済の社会的意義はとても高いのではないでしょうか。